「カリタスの家」について
| 「カリタスの家」案内 |
| アクセス |
| カリタスジャパンの「委員会報告」より |
| カリタス通信第6号 |
| ノーマライゼーション やさしさとデザイン ハンディキャッパーの自立と支援 |

毎日新聞17.1.1
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
tamon:カリタス 1 [(ラテン) caritas]
福祉的行為の三原型の一。人類愛のこと。ギリシャ語のアガペーにあたる。
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
※注(1)
以下は「カリタスの家」ホームページより
http://www.mt-japan.co.jp/caritas/index2.html
「カリタスの家」案内
◆設置年月日 平成10年9月1日開所 ◆種 別 知的障害者援護施設 更生施設(入所) ◆経営主体 社会福祉法人 かいたっくす 理事長 滑石七五三夫 ◆施設名 カリタスの家 施設長 原田芳枝 ◆入所定員 重度棟 20人 一般棟 10人 ショートステイ 3人 強度行動障害特別処遇事業 4人 通所部 10人 ◆施設規模 敷地面積 17,500㎡ 建物面積 1,350.01㎡ 構造 鉄筋コンクリート平家建 冷暖房完備 居室 2人部屋 16室 1人部屋 5室 〒820-1111 福岡県嘉穂郡頴田町大字勢田字新立119-14 |
※注(2)
このホームページの最終更新は大部古いようで、
「カリタス通信」は第6号平成12年8月19日で終わっている。
施設長は原田芳枝となっているが、現在のカリタスの家の施設長は原田秀樹氏。
原田秀樹氏は原田芳枝氏の長男。
原田芳枝氏は、カリタスの家の開設当初から15年春まで施設長を務めた。
現在は県運営の自閉症・発達障害支援センター「ハレルヤ館」のセンター長。
アクセス
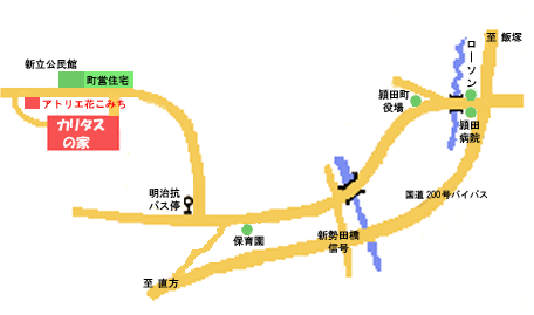
http://www.caritas.jp/234/07_iinkai.html
カリタスジャパンの「委員会報告」より
2004年9月6日~9月29日
日 時
2004年9月6日(月) 11:30~16:30
場 所
日本カトリック会館 会議室6
出席者
小宇佐敬二、敷島康雄、下口 勲(以上委員)、森園靖信(大分教区)、野坂秀男(秘書)
議 題
「全国教区担当者会議日程、議題について」
2004年10月11日~13日に実施される2004年度定例全国担当者会議に関して以下の通り審議された。
審議事項
会議日程
第1日目(10月11日(月))
14:00 講演会『今、子どもの心が危ない』原田芳枝氏(福祉法人「福岡カリタスの家」、
重度心身障害者自立の家「モニカの家」主宰者)
第2日目(10月12日(火))
09:00 会議(1) 全体会議
13:00 会議(2) 分科会
第3日目(10月13日(水))
09:00 会議(3) 全体会議
13:00 会議(4) 行動計画、事務局報告
講演会内容
長崎の同級生殺害事件に即する内容であることを確認する。
主宰者はカリタスジャパン、大分教区が後援、共催である。
全体会議議題
社会福祉活動ネットワーク構築に向けて、カトリック福祉活動の共通理解を保持し、理解する。
社会福祉の現状に関するアンケートの主旨を確認し、カトリック福祉概念とカトリック福祉概念の違いを明確にする。
カリタスジャパン教区担当者会の役割を確認する。
庶務事項を確認した。
2004年9月6日(月) 11:30~16:30
場 所
日本カトリック会館 会議室6
出席者
小宇佐敬二、敷島康雄、下口 勲(以上委員)、森園靖信(大分教区)、野坂秀男(秘書)
議 題
「全国教区担当者会議日程、議題について」
2004年10月11日~13日に実施される2004年度定例全国担当者会議に関して以下の通り審議された。
審議事項
会議日程
第1日目(10月11日(月))
14:00 講演会『今、子どもの心が危ない』原田芳枝氏(福祉法人「福岡カリタスの家」、
重度心身障害者自立の家「モニカの家」主宰者)
第2日目(10月12日(火))
09:00 会議(1) 全体会議
13:00 会議(2) 分科会
第3日目(10月13日(水))
09:00 会議(3) 全体会議
13:00 会議(4) 行動計画、事務局報告
講演会内容
長崎の同級生殺害事件に即する内容であることを確認する。
主宰者はカリタスジャパン、大分教区が後援、共催である。
全体会議議題
社会福祉活動ネットワーク構築に向けて、カトリック福祉活動の共通理解を保持し、理解する。
社会福祉の現状に関するアンケートの主旨を確認し、カトリック福祉概念とカトリック福祉概念の違いを明確にする。
カリタスジャパン教区担当者会の役割を確認する。
庶務事項を確認した。
カリタスジャパンがいかなる団体か、よく分かっておりません。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
http://www.caritas.jp/234/07_iinkai.html
カリタス通信第6号
-平成12年8月19日-
平成十五年より、障害者施設も従来の措置制度より、契約制度へと大きく変わります。
施設と、利用者とが対等な位置関係となり、利用者の自己決定で、施設と利用契約を結ぶことになるのです。しかし、強
度行動障害を背負う人達にとって、選択できるほどの施設はありません。社会の片隅に、置いてきぼりになっていた人
達です。この人達にとって何よりも大事なことは、施設の専門性です。
専門施設で適切な療育を受けることで、人としての当たり前の暮らしが得られるのです。家族での介護は不可能な人
達にこそ、福祉サービスの提供が必要なのに、繰り返される行動の凄まじさにたじろぎ、自閉症の人達の行動を理解さ
れ難い社会の中で、暗黒の荒海にかろうじて点滅している一筋の灯りのように、専門施設というにはおこがましい、カリ
タスの家を頼みの綱として、この場を選ばれたのです。
4月1日から、強度行動障害特別処遇事業が始まりました。福岡県下では、私どもが初めての取り組みです。この取り
組みによって、私ども施設の真価が問われ、療育方針の確立を得ることになると考えております。
自閉症の人達の療育方法は、さまざまですが、療育の基本は、「心」だと私は思います。私たちは、行動障害のある人
達の行動を、私たちの尺度で計って問題行動と決めています。しかし、その人達にとっては問題行動ではなく、ひとつ
のコミュニケーションの方法でしかないのです。しかし、その人達が生活する上では、やはり無くさなければいけない行
動です。そのために私たちは、まず「その行動をなぜ起こすのか」ということから始めます。行動障害のある人達はコミ
ュニケーションを取るための表現の仕方が少し下手なだけです。それをきちっと理解できない人達が、間違った係わり
方をするために、問題行動がひどくなっていくのです。いわば強度行動障害は、二次障害といっても過言ではないと思
います。
そこで私たちは、問題行動の起きたときの心の叫びにきちっと耳を傾け、そのサインを理解し、不安定な心を満たして
あげる。けっして威張らず、焦らずをモットーにして、今まで理解されなかった心を、一つ一つ、ひとりの人として理解を
し、心を常に忘れることなく係わっています。その成果は確実に上がっています。一年前よりも今日、みんなの表情は
良く、落着いてきました。十数年かかってつくられた性格は、けっして短期間で変わるはずはありません。しかし、一年
一年確実にみんな成長していっています。カリタスの家に入所している人達みんなが、私たちにいろんな事を教えてく
れます。そして私たちの心を大きく成長させてくれます。
私達は、その人達の尊厳を守りながら、共に笑い、共に泣き、表情の変化に喜び合い、毎日、療育に励んでおります。
私達は、地域の人達に強度行動障害を背負う人達の苦悩と現実を理解されて、地域の中で共に生きる日の来ることを
願っております。
施設と、利用者とが対等な位置関係となり、利用者の自己決定で、施設と利用契約を結ぶことになるのです。しかし、強
度行動障害を背負う人達にとって、選択できるほどの施設はありません。社会の片隅に、置いてきぼりになっていた人
達です。この人達にとって何よりも大事なことは、施設の専門性です。
専門施設で適切な療育を受けることで、人としての当たり前の暮らしが得られるのです。家族での介護は不可能な人
達にこそ、福祉サービスの提供が必要なのに、繰り返される行動の凄まじさにたじろぎ、自閉症の人達の行動を理解さ
れ難い社会の中で、暗黒の荒海にかろうじて点滅している一筋の灯りのように、専門施設というにはおこがましい、カリ
タスの家を頼みの綱として、この場を選ばれたのです。
4月1日から、強度行動障害特別処遇事業が始まりました。福岡県下では、私どもが初めての取り組みです。この取り
組みによって、私ども施設の真価が問われ、療育方針の確立を得ることになると考えております。
自閉症の人達の療育方法は、さまざまですが、療育の基本は、「心」だと私は思います。私たちは、行動障害のある人
達の行動を、私たちの尺度で計って問題行動と決めています。しかし、その人達にとっては問題行動ではなく、ひとつ
のコミュニケーションの方法でしかないのです。しかし、その人達が生活する上では、やはり無くさなければいけない行
動です。そのために私たちは、まず「その行動をなぜ起こすのか」ということから始めます。行動障害のある人達はコミ
ュニケーションを取るための表現の仕方が少し下手なだけです。それをきちっと理解できない人達が、間違った係わり
方をするために、問題行動がひどくなっていくのです。いわば強度行動障害は、二次障害といっても過言ではないと思
います。
そこで私たちは、問題行動の起きたときの心の叫びにきちっと耳を傾け、そのサインを理解し、不安定な心を満たして
あげる。けっして威張らず、焦らずをモットーにして、今まで理解されなかった心を、一つ一つ、ひとりの人として理解を
し、心を常に忘れることなく係わっています。その成果は確実に上がっています。一年前よりも今日、みんなの表情は
良く、落着いてきました。十数年かかってつくられた性格は、けっして短期間で変わるはずはありません。しかし、一年
一年確実にみんな成長していっています。カリタスの家に入所している人達みんなが、私たちにいろんな事を教えてく
れます。そして私たちの心を大きく成長させてくれます。
私達は、その人達の尊厳を守りながら、共に笑い、共に泣き、表情の変化に喜び合い、毎日、療育に励んでおります。
私達は、地域の人達に強度行動障害を背負う人達の苦悩と現実を理解されて、地域の中で共に生きる日の来ることを
願っております。
※注(3)
カリタス通信は第3号より第6号までで
http://www4.ocn.ne.jp/~caritas/karitu.htm
に掲載されています。
■ケーススタディ
ノーマライゼーション やさしさとデザイン
ハンディキャッパーの自立と支援
スワンカフェ銀座店/カリタスの家
関連記事/ケーススタディ・博物館と福祉のコラボレーション
ケーススタディ・スウェーデンにみるやさしさのデザイン
トーク・トップインタビュー 小倉昌男氏
--------------------------------------------------------------------------------
1990年、「障害を持つアメリカ人法(American with Disabilities Act=略称 ADA)」が設立された。そのとき、ADAの生みの親といわれる障害援助
活動家のジャスティン・ダート氏は、「障害を持つ人が職を得ることができれば、収入も増え、消費者としても力をもつことになる」と語ったという。
そのときから「税金によって生活していた人が、職を得ることによって税金を納める存在になった」。障害のある人もない人も、同じように普通の生
活を送る、これがノーマライゼーションの本質である。
このノーマライゼーションという概念にしたがって、私たちも「障害」に対する「やさしさ」や「道徳観」を変えなければならないだろう。健常者が当然
のようにもつ欲求や嗜好は、障害者や痴呆症の患者でも同じようにもっているものである。障害者だからといって特別視したり、特別な扱いをした
りすることは、必ずしも障害者に対するやさしさとイコールではない。
最近では、バリアフリーの考え方を超えて、ユニバーサルデザインに代表されるような、「障害の有無に関係なく自然に使える美しいデザイン」が
評価される時代になりつつある。これはデザインの世界のノーマライゼーションである。
いまの時代、私たちは何をすることができるのか、真摯に考えてみたい。
炭焼きを通じて障害者に働く喜びを感じてもらう
働き、ものをつくり、それが売れることで得られる喜び……、健常者であれば誰もが感じることのできる、働く喜びを障害者にも与えてあげたい。
そんな思いからスタートしたのが、福岡県嘉穂郡頴田町の知的障害者更生施設「カリタスの家」で行なわれている炭焼きである。
カリタスの家は、福岡県でも障害の重い人たちを対象とする施設で、遠賀川上流の飯塚市郊外にあたる、緑豊かな住宅地の高台に位置する。こ
こに「凛光窯」と名づけられた炭焼き窯がつくられたのは、2001年7月のこと。障害者が働くための具体的な支援をしていこうと設立されたヤマト運
輸(株)の子会社、(株)スワンネットのプロデュースを受けけて開設されたものである。同時に同社が、ここで焼かれた炭を買上げ、ヤマト運輸の全
国ネットの宅急便ネットワークを活かして一般に販売していくという流通ルートも確立している。
「障害者になぜ炭焼きがいいかというと、シンプルで短い作業が連続して行なえるからです。木を決まった長さに切る、それを運ぶ、窯に詰めると
いうように、短い作業を繰り返し、積み重ねていくことで炭は完成します。どんなに障害の重い人でも、切っている木を押さえているということはでき
る。それもひとつの作業になるのです」(指導部長・原田秀樹氏)。
ここではそうやって、比較的障害の軽い人が重い人を助けながら、班による作業分担が行なわれている。日々の作業を繰り返しているうちに、そ
れまで木を押さえることしかできなかった人が進んでノコギリをもち、木を切るようになるのだという。
実際には言葉でいうほど簡単なことではないのだろうが、「やはり障害者も、私たちと同じように働きたいのです。毎日、10分でも15分でもいいか
ら仕事に出て働くことで生活のリズムも生まれる。それは健常者でも障害者でも同じ、大切なことなのです」(原田氏)。そして、もっと重要なのは、
それが売れるということだ。いくら目標が立派でも、売れないものをつくり続けていては、やがて意欲すら失ってしまう。自分たちがつくったものを買
ってくれる=必要としてくれる人がいて、はじめて喜びが生まれる。その結果として報酬があるのだ。
「これはあなたが働いたものだよ、といって手渡してあげれば、誰でも嬉しいものです。その点で、スワンネットさんが販売を担当してくださること
の意義は非常に大きいと思っています。近隣から炭焼きの臭い対策を求められ、高額な脱臭装置を据え付けざるを得なかったため、そのリース料
の負担が重い。このリース料の支払いが終われば採算に乗せられるので、そのときを楽しみに、いまは、がんばっています。やがては障害者がそ
の報酬で生活していけるようになるのが理想です」。
そのためにも、いま、炭を焼くことで生じる灰や炭粉などを利用した石鹸やシャンプーなど、カリタスの家ブランドのオリジナル商品を開発し、独自
の販売ルートの開拓にもチャレンジしている。「障害者がつくったものだからということではなく、一般の商品と同じように売れるものにしていきたい」
(原田氏)と、炭焼きを契機に、次なる目標がどんどんと生まれている。
そんな思いからスタートしたのが、福岡県嘉穂郡頴田町の知的障害者更生施設「カリタスの家」で行なわれている炭焼きである。
カリタスの家は、福岡県でも障害の重い人たちを対象とする施設で、遠賀川上流の飯塚市郊外にあたる、緑豊かな住宅地の高台に位置する。こ
こに「凛光窯」と名づけられた炭焼き窯がつくられたのは、2001年7月のこと。障害者が働くための具体的な支援をしていこうと設立されたヤマト運
輸(株)の子会社、(株)スワンネットのプロデュースを受けけて開設されたものである。同時に同社が、ここで焼かれた炭を買上げ、ヤマト運輸の全
国ネットの宅急便ネットワークを活かして一般に販売していくという流通ルートも確立している。
「障害者になぜ炭焼きがいいかというと、シンプルで短い作業が連続して行なえるからです。木を決まった長さに切る、それを運ぶ、窯に詰めると
いうように、短い作業を繰り返し、積み重ねていくことで炭は完成します。どんなに障害の重い人でも、切っている木を押さえているということはでき
る。それもひとつの作業になるのです」(指導部長・原田秀樹氏)。
ここではそうやって、比較的障害の軽い人が重い人を助けながら、班による作業分担が行なわれている。日々の作業を繰り返しているうちに、そ
れまで木を押さえることしかできなかった人が進んでノコギリをもち、木を切るようになるのだという。
実際には言葉でいうほど簡単なことではないのだろうが、「やはり障害者も、私たちと同じように働きたいのです。毎日、10分でも15分でもいいか
ら仕事に出て働くことで生活のリズムも生まれる。それは健常者でも障害者でも同じ、大切なことなのです」(原田氏)。そして、もっと重要なのは、
それが売れるということだ。いくら目標が立派でも、売れないものをつくり続けていては、やがて意欲すら失ってしまう。自分たちがつくったものを買
ってくれる=必要としてくれる人がいて、はじめて喜びが生まれる。その結果として報酬があるのだ。
「これはあなたが働いたものだよ、といって手渡してあげれば、誰でも嬉しいものです。その点で、スワンネットさんが販売を担当してくださること
の意義は非常に大きいと思っています。近隣から炭焼きの臭い対策を求められ、高額な脱臭装置を据え付けざるを得なかったため、そのリース料
の負担が重い。このリース料の支払いが終われば採算に乗せられるので、そのときを楽しみに、いまは、がんばっています。やがては障害者がそ
の報酬で生活していけるようになるのが理想です」。
そのためにも、いま、炭を焼くことで生じる灰や炭粉などを利用した石鹸やシャンプーなど、カリタスの家ブランドのオリジナル商品を開発し、独自
の販売ルートの開拓にもチャレンジしている。「障害者がつくったものだからということではなく、一般の商品と同じように売れるものにしていきたい」
(原田氏)と、炭焼きを契機に、次なる目標がどんどんと生まれている。



(左)●炭窯は、重度の知的障害者が運用することを考慮して、耐火煉瓦と耐火セメントで丈夫に、扱いやすいように小型に、それでも出炭量を
増やせるように7基つくられている
(中)●焼き上がった炭は同じ大きさに切り揃えられ、きちんと収まるように箱詰めして出荷を待つ
(右)●この窯では、炭を焼くための木材の窯詰めが行なわれている。煙や臭いで近隣に迷惑がかからないよう、脱臭装置を取り付けている
増やせるように7基つくられている
(中)●焼き上がった炭は同じ大きさに切り揃えられ、きちんと収まるように箱詰めして出荷を待つ
(右)●この窯では、炭を焼くための木材の窯詰めが行なわれている。煙や臭いで近隣に迷惑がかからないよう、脱臭装置を取り付けている



(左)●炭焼きに伴ってできる木酢液をボトルに詰める。これも大切な作業のひとつだ
(中)●人に頼るだけでなく自分たちでも売れるものをつくっていこうとの前向きな姿勢から、シャンプー、石鹸などの新しい商品が生まれている
(右)●敷地内にある自閉症自立支援センター。1階では訓練・相談業務などを行ない、2階には障害を克服して自立に向けて活動する人たちと職
員の生活の場として個室がある
(中)●人に頼るだけでなく自分たちでも売れるものをつくっていこうとの前向きな姿勢から、シャンプー、石鹸などの新しい商品が生まれている
(右)●敷地内にある自閉症自立支援センター。1階では訓練・相談業務などを行ない、2階には障害を克服して自立に向けて活動する人たちと職
員の生活の場として個室がある
|
|

